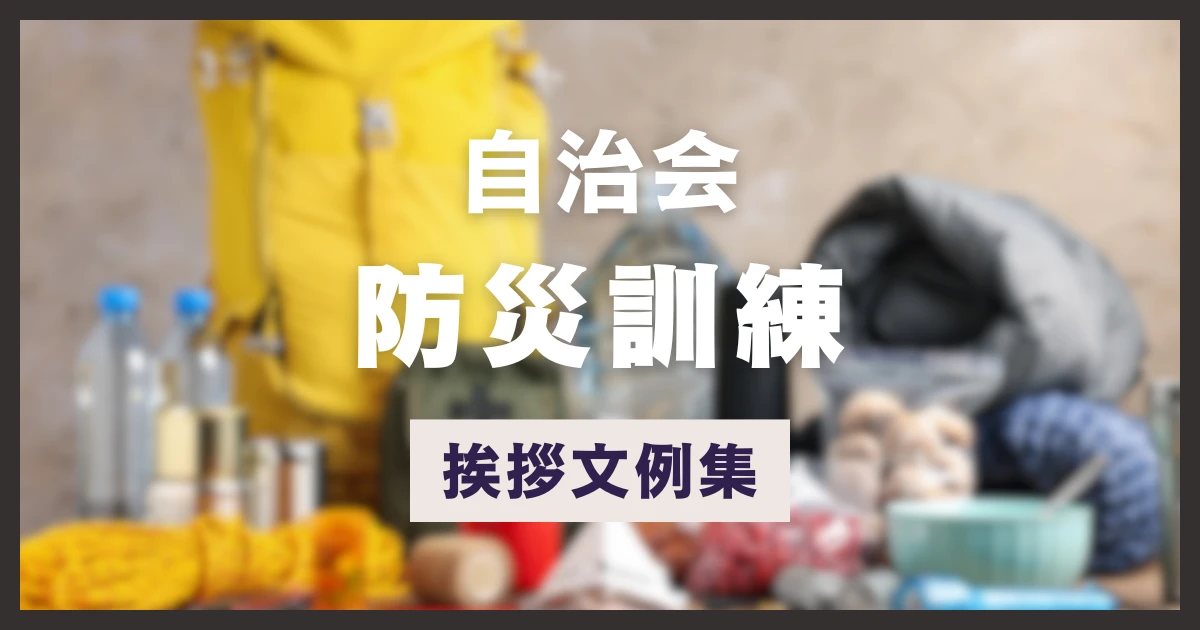防災訓練で挨拶を任されると、
「何を話せばいいのか分からない」
「長くならずに簡単にまとめたい」
と悩む方は多いと思います。
実際、防災訓練では 自治会長の開会・閉会挨拶 と、防災部長による訓練説明 という2つの役割があり、それぞれ伝える内容が違います。
この記事では、訓練の一般的な流れを押さえながら、すぐに使える挨拶文例をフォーマル・ショート・くだけた調子でまとめました。
防災訓練の一般的な流れ
防災訓練は、地域や規模によって内容が少し変わりますが、一般的には次のような流れで進みます。
- 受付
- 参加者が集まり、名簿の確認や配布物を受け取る。
- 自治会長の開会挨拶
- 訓練の始まりを告げ、参加への感謝や目的を簡潔に伝える。
- 防災部長による訓練の説明
- 本日の流れや注意点を伝え、スムーズに進行できるよう案内する。
- 消防署や指導員による実演
- 心臓マッサージやAEDの使い方、初期消火の方法などを説明・実演。
- 実技体験
- 参加者が実際に心臓マッサージや消火器の操作を体験する。
- 全体の振り返り
- 今日学んだことを共有し、災害時の意識を確認する。
- 自治会長の閉会挨拶
- 訓練を無事終えられた感謝と、日常での備えの大切さを伝えて締める。
挨拶のタイミングは、開会時(自治会長)・訓練導入時(防災部長)・閉会時(自治会長) の3回が基本です。
自治会長の開会挨拶
フォーマル
パターン1
皆さま、本日は自治会の防災訓練にご参加いただき、誠にありがとうございます。
近年、地震や豪雨、火災など、予測できない災害が全国各地で発生しています。
災害時に私たちが自分の身を守り、周囲と助け合うためには、日頃の備えと訓練が欠かせません。
本日は消防署の皆さまにもお力添えいただき、心臓マッサージやAEDの使い方、消火器による初期消火など、実践的な内容を学べる貴重な機会となっております。
どうぞ最後まで真剣に取り組んでいただき、学んだことを日常の生活に活かしていただければ幸いです。
パターン2
皆さま、本日はお忙しい中、防災訓練にご参加いただきありがとうございます。
災害はいつ、どこで起こるかわかりません。日常生活の中で「自分は大丈夫」と思い込んでいると、いざという時に行動できないものです。
今日の訓練では、消防署の方から直接ご指導をいただきながら、応急処置や消火の方法を体験していただきます。
この学びを通じて、ご自身だけでなく、ご家族や地域を守る力をつけていただければと願っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
シンプル
パターン1
本日は防災訓練にお集まりいただき、ありがとうございます。
災害は突然やってきます。今日の体験は、皆さんが「いざ」という時に冷静に行動する助けになるはずです。
最後まで安全に取り組み、有意義な時間にしていただければと思います。
パターン2
皆さま、ご参加ありがとうございます。
防災は一人の力だけではなく、地域みんなで取り組むものです。
今日の訓練を通じて、改めて「助け合いの大切さ」を感じていただければ幸いです。
パターン3
本日は防災訓練にお越しいただきありがとうございます。
消防署の方々に直接ご指導いただきながら体験できる貴重な機会です。
ぜひ積極的に参加し、日常の備えに活かしてください。
パターン4
お集まりいただきありがとうございます。
今日の訓練は短い時間ですが、心臓マッサージやAED、消火器の使い方を体験できる大事な機会です。
一つでも「覚えた」と思えることを持ち帰っていただければ嬉しいです。
パターン5
ご参加ありがとうございます。
今日の訓練は難しいものではありません。実際に体験することで「自分にもできる」と感じられると思います。
安全第一で、一緒に学んでいきましょう。
親しみのある挨拶
パターン1
皆さん、今日は集まっていただきありがとうございます。
防災訓練と聞くと堅苦しく感じるかもしれませんが、実際にやってみると意外と楽しく学べます。
消防署の方の説明を聞きながら、気軽な気持ちで参加してください。
今日の体験が「いざという時」に必ず役に立つと思います。
パターン2
皆さん、こんにちは。
今日は心臓マッサージやAEDの使い方、消火器を使った消火訓練などを体験します。
普段はなかなかできないことばかりなので、楽しみながら学んでいただければと思います。
安全に気を付けつつ、元気に取り組んでいきましょう。
パターン3
今日はご参加ありがとうございます。
災害はいつ起きるかわからないからこそ、こうした訓練が大切です。
難しく考えず、「遊びの延長」くらいの気持ちで大丈夫ですので、まずは体を動かしてみてください。
それでは一緒に頑張っていきましょう。
防災部長の訓練説明
フォーマル
パターン1
皆さま、本日は防災訓練にご参加いただき、ありがとうございます。
本日の流れをご説明いたします。
まず、消防署の方より心臓マッサージとAEDの使い方を実演していただきます。
その後、皆さまにもグループごとに体験していただきます。
続いて、消火器を使った初期消火の訓練を行い、最後に全員で振り返りを行って終了です。
訓練中は安全第一で行動し、スタッフの指示に従っていただきますようお願いいたします。
パターン2
本日の訓練内容についてご説明いたします。
今日は大きく三つの体験をしていただきます。
一つ目は「心臓マッサージとAEDの使用方法」、二つ目は「消火器による初期消火」、三つ目は「避難の仕方と安全確認」です。
各体験はグループごとに順番に回っていただきますので、落ち着いて取り組んでください。
訓練中に不明な点があれば、その場でスタッフにお尋ねいただければと思います。
シンプル
パターン1
これからの流れをご説明します。
まず消防署の方の実演を見て、そのあと皆さんに心臓マッサージやAEDを体験していただきます。
続いて消火器の練習をし、最後に振り返りをして終了です。
パターン2
本日の訓練は「心臓マッサージ」「AEDの使い方」「消火器による消火」を中心に進めます。
グループごとに順番に体験しますので、慌てず安全に取り組んでください。
パターン3
今日の訓練は短い時間ですが、実際に体験できる内容が多いです。
消防署の指導を受けながら、一つひとつ確認していきましょう。
パターン4
本日は応急処置と初期消火を中心に練習します。
普段なかなか経験できないことですので、ぜひ積極的に体験してください。
パターン5
訓練の流れはとてもシンプルです。
実演を見て、実際に体験し、最後に振り返る――この三つだけです。
気楽に参加してみてください。
親しみのある挨拶
パターン1
今日は「心臓マッサージ」「AED」「消火器」と、普段はなかなか体験できないものを用意しました。
最初は難しく感じても、やってみると案外できるものです。
気楽に体験してみてくださいね。
パターン2
今日の訓練は堅苦しい講義ではなく、体を動かしながら楽しく学べる内容になっています。
消防署の方が分かりやすく教えてくれますので、安心して取り組んでください。
パターン3
本日は気軽に学べる内容になっています。
遊びのつもりで体験しても構いません。やってみることで自然と身につくことがたくさんありますので、ぜひ楽しんでください。
自治会長の閉会挨拶(防災訓練)
フォーマル
パターン1
皆さま、本日は防災訓練に最後までご参加いただき、誠にありがとうございました。
消防署の皆さまのご指導のもと、心臓マッサージやAEDの使用方法、消火器の操作など、実際に体を動かしながら学ぶことができました。
災害はいつ発生するかわかりませんが、今日の経験を積み重ねておくことで、万一の際に冷静に行動することができます。
どうか今日学んだことをご家庭やご近所で共有し、日常の備えにつなげていただければと思います。
今後も地域全体で協力し合い、安心して暮らせる町をつくっていきましょう。これをもちまして、本日の防災訓練を終了いたします。
パターン2
本日はお忙しい中、防災訓練にご参加いただき、誠にありがとうございました。
訓練を通じて改めて感じるのは、災害時に大切なのは「一人ひとりの備え」と「地域の助け合い」であるということです。
応急処置や初期消火の方法を学んだことで、「自分にもできる」という自信を持っていただけたのではないでしょうか。
ぜひ今日の学びを忘れず、日常の生活に取り入れていただきたいと思います。
来年以降もこのような訓練を続けながら、地域全体で防災力を高めてまいりましょう。これにて閉会の挨拶とさせていただきます。
シンプル
パターン1
本日は防災訓練にご参加いただきありがとうございました。
今日の体験を通して、災害時にどう動けばよいのかを少しイメージできたと思います。
ぜひご家庭でも話題にしていただき、備えを続けていただければ幸いです。
これで本日の訓練を終了いたします。
パターン2
皆さま、本日はご協力ありがとうございました。
心臓マッサージや消火器の使い方など、実際にやってみて「思ったより難しい」と感じた方もいらっしゃるかと思います。
その気づきこそが大切で、今後の備えにつながります。
今日学んだことをぜひ思い出し、日々の生活に取り入れてください。
パターン3
ご参加ありがとうございました。
災害はいつ起こるかわかりませんが、今日のように地域全体で備えておくことが、一番の安心につながります。
これからも力を合わせて、安全な地域をつくっていきましょう。
パターン4
皆さん、お疲れさまでした。
本日の訓練で得た知識や体験を、それぞれの家庭や職場に持ち帰って活かしていただければ嬉しく思います。
今後も引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。
親しみのある挨拶
パターン1
皆さん、今日は本当にお疲れさまでした。
やってみると「意外とできた」と感じた方もいれば、「難しいな」と思った方もいるかもしれません。
どちらにしても、体験してみたこと自体が大きな収穫です。
ぜひご家庭でも「いざという時どうするか」を話し合ってみてください。
今日の経験が皆さんの安心につながれば幸いです。
パターン2
今日の訓練はいかがでしたか?
普段はなかなかできない体験ばかりでしたので、きっと印象に残ったと思います。
災害は突然やってきますが、今日の経験を思い出せば、落ち着いて行動できるはずです。
今後も地域の仲間同士で助け合いながら、安全に暮らしていきましょう。
パターン3
皆さん、今日はご参加ありがとうございました。
消防署の方に教わりながら体験できたことで、防災が少し身近に感じられたのではないでしょうか。
これからも気軽に参加できる訓練を続けていきたいと思いますので、また次回もよろしくお願いします。
それでは、どうぞお気をつけてお帰りください。
アレンジのコツ
- 地域事情を入れる
例:地震が多い地域なら「家具の固定を忘れずに」、水害が多い地域なら「避難場所の確認を」など。 - 参加者層に合わせる
子どもが多ければ「遊び感覚で学んで」など軽めに、大人中心なら「家庭や地域で実践を」など真面目に。 - 消防署や講師への感謝を加える
「専門的なご指導をいただき感謝いたします」など一言添えると場が締まる。 - 体験内容を具体的に触れる
「今日体験したAEDの使い方」などを挨拶に入れるとリアリティが出る。 - 自分の言葉を少し足す
「私自身も初めて体験して勉強になりました」など、自分の感想を一言加えると自然で親しみやすい。
ダメな挨拶例
- 長すぎる挨拶
例:「地震の歴史を振り返りますと、江戸時代には…昭和には…」と延々と語る。 - 自分本位な内容
例:「今回の訓練は、私が中心となって計画しました。私の努力が…」と手柄を強調する。 - 脅し口調になる
例:「大地震が来たら必ず死者が出ます。今訓練しないと取り返しがつきません!」と恐怖を煽る。 - 専門用語ばかり
例:「一次救命処置、バイタルサイン、ACLSに基づいた…」と難しい言葉を並べる。 - 地域を軽んじる発言
例:「うちの地域はどうせ小さいから、大した備えは必要ありません」など。
まとめ
防災訓練での挨拶は、自治会長と防災部長で役割が異なります。
- 自治会長は「参加への感謝」「地域の一体感」「安心感」を伝えることが中心
- 防災部長は「訓練の流れや注意点」を分かりやすく説明することが役割です
基本は「感謝+安全+前向きな言葉」。
長くなりすぎず、30秒〜1分でまとめるのがポイントです。
本記事で紹介した文例をそのまま使っても、少しアレンジしても大丈夫。
地域に合った言葉で伝えることで、より自然な挨拶になります。