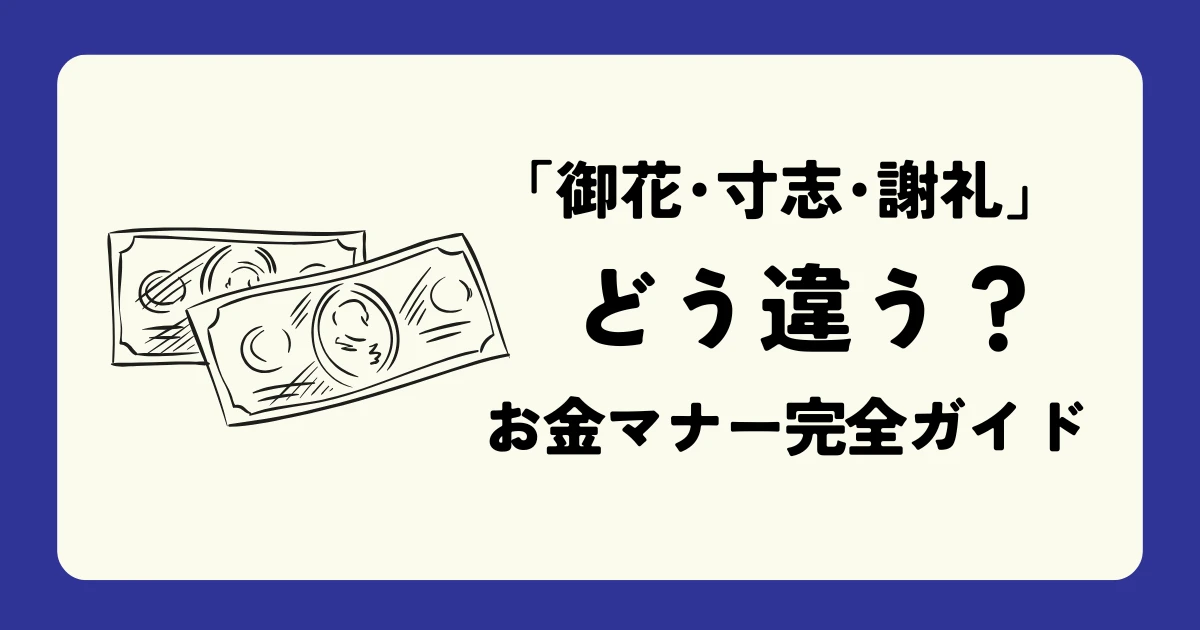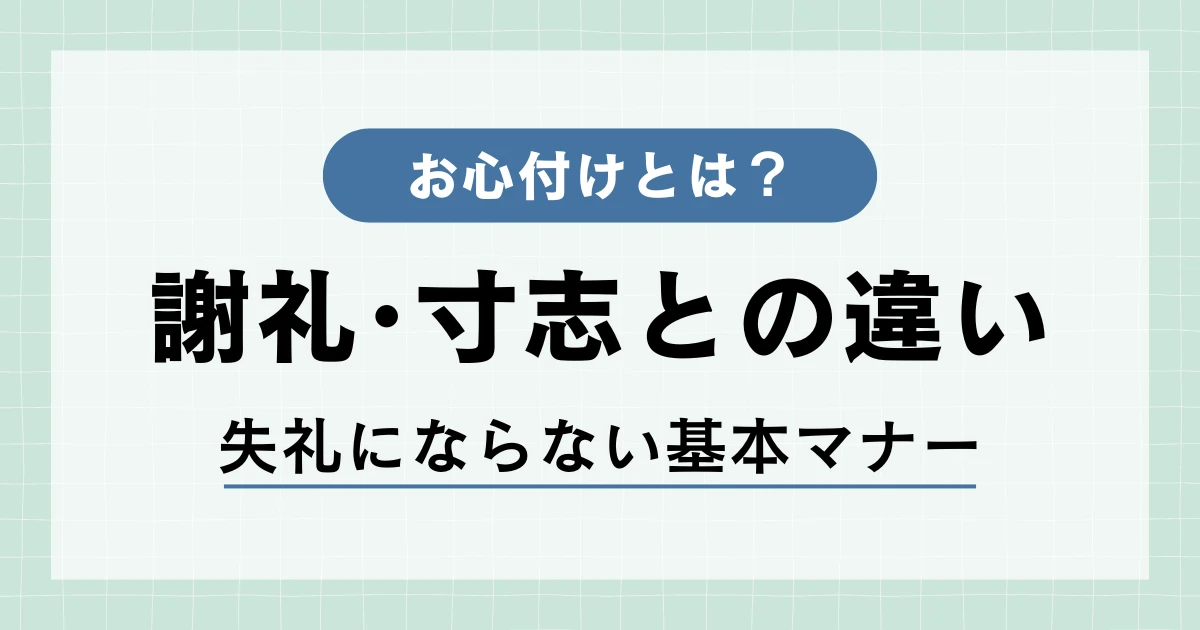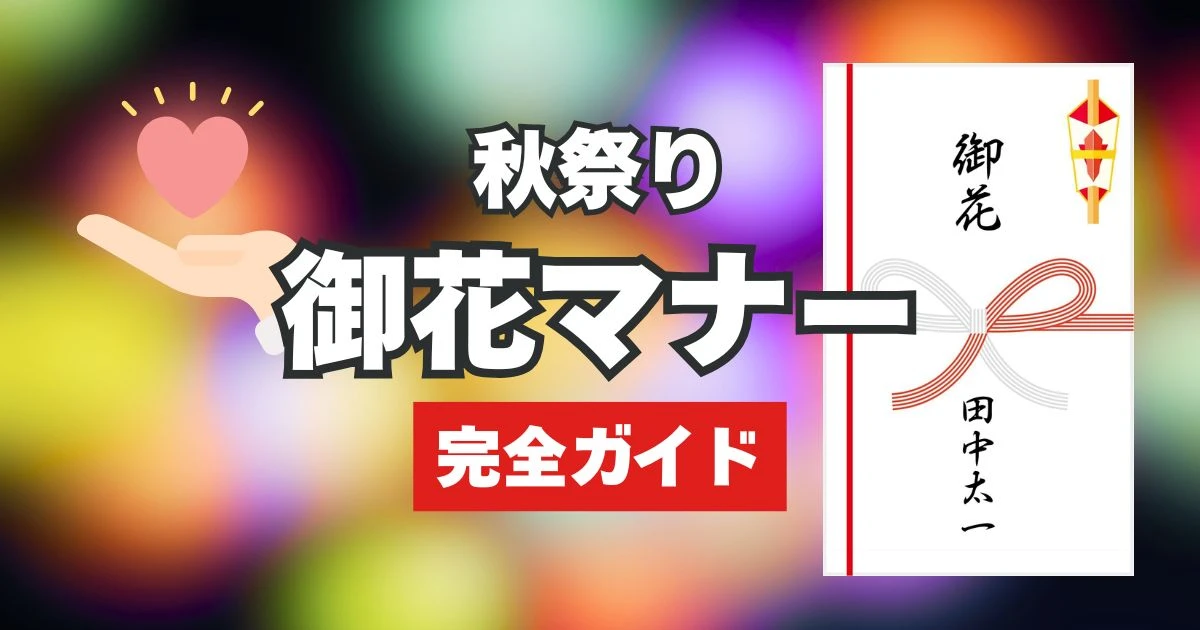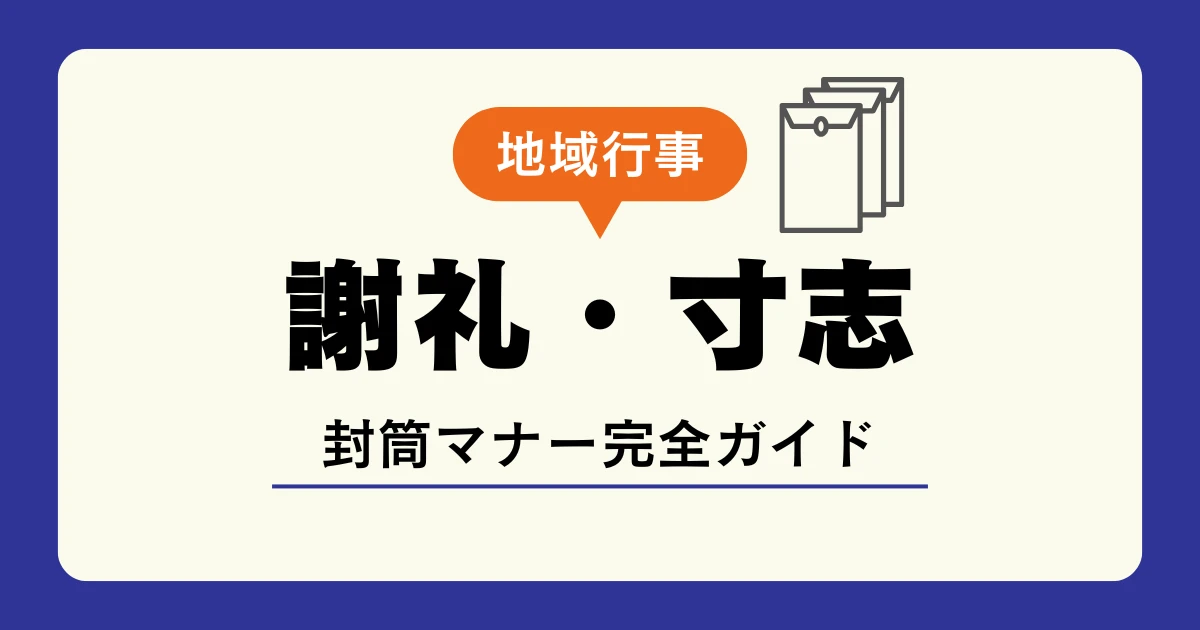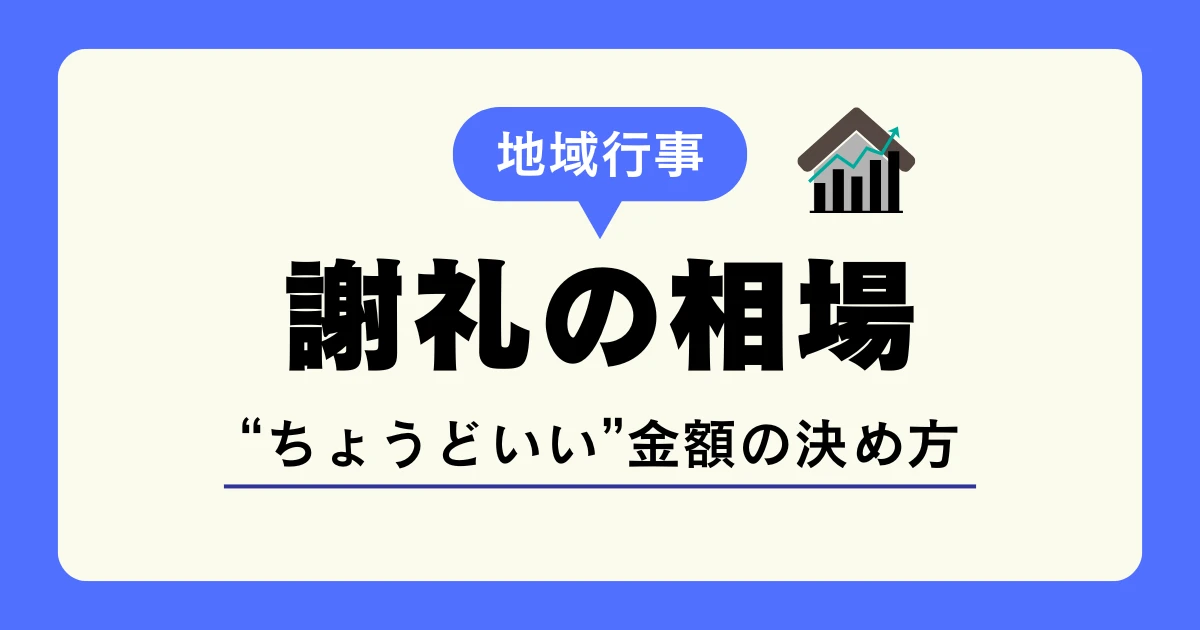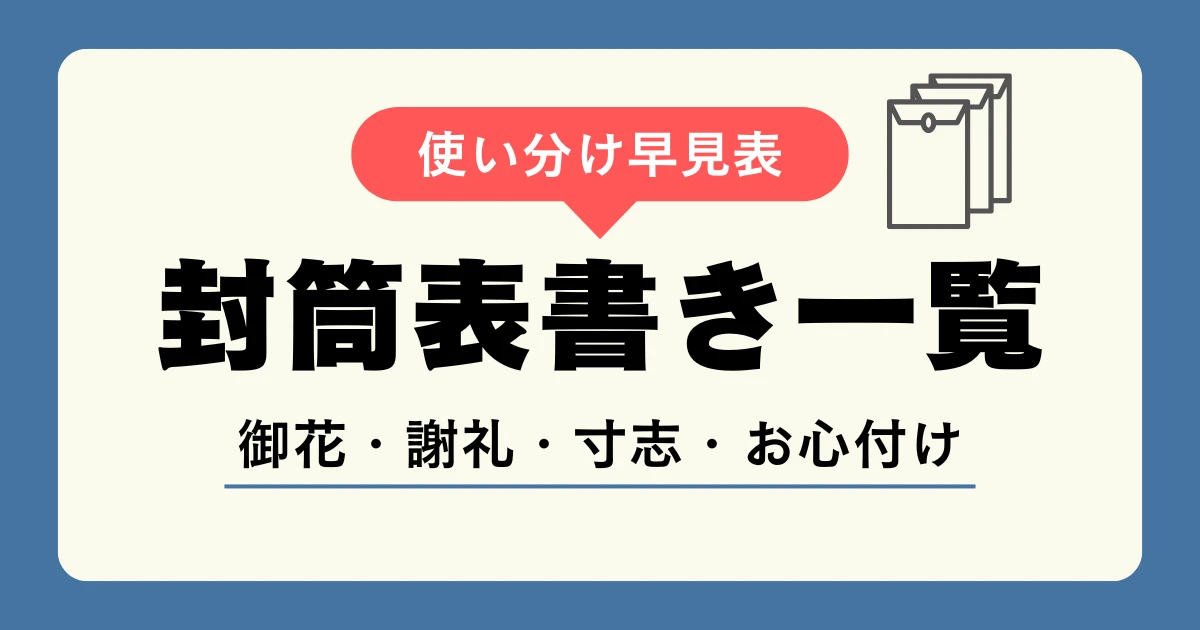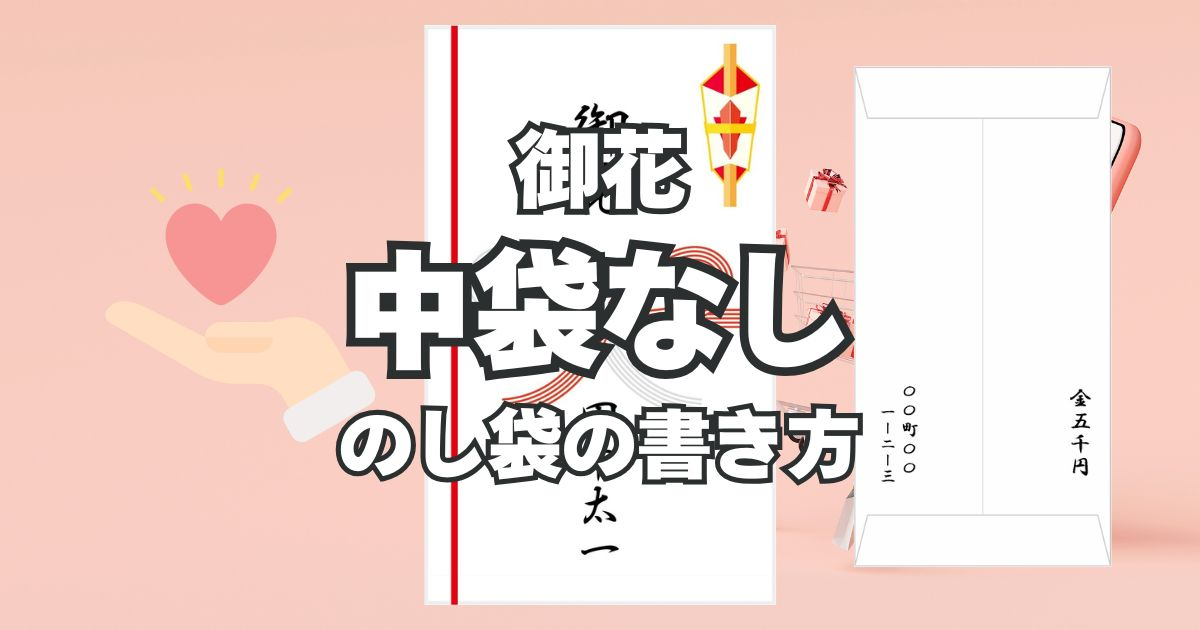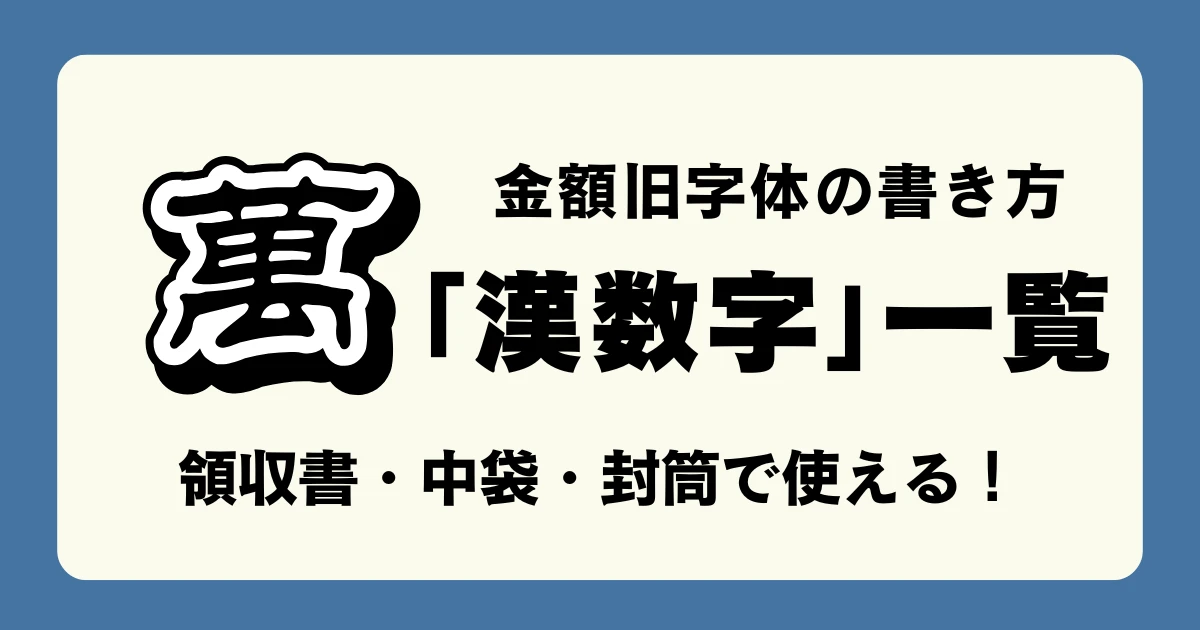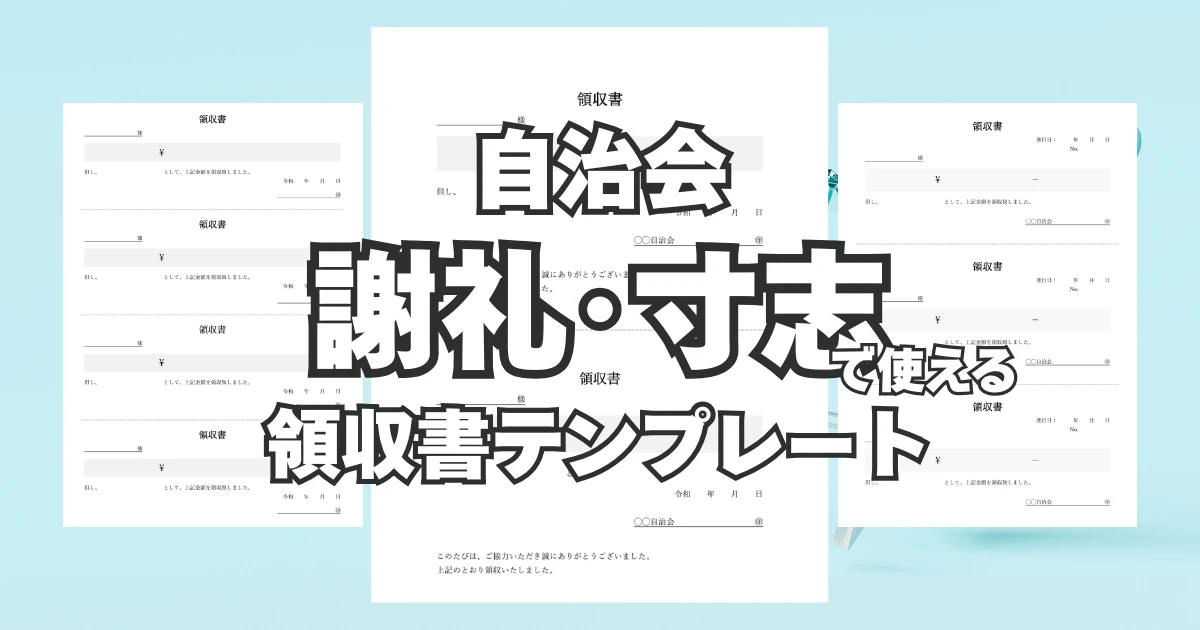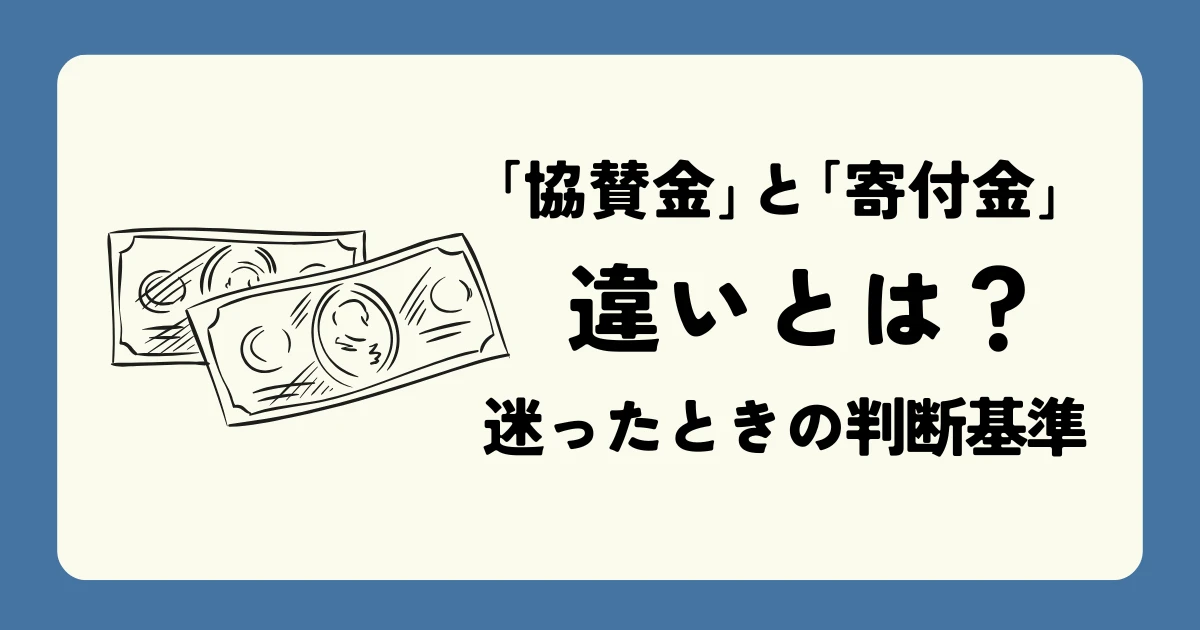自治会や地域行事では、「御花」「寸志」「謝礼」など、お金を包む場面がたびたびあります。
どれを使えばいいのか、言葉の違いに迷った経験はありませんか?
実はこの3つの言葉は、使う相手や目的によって意味がまったく違います。
形式よりも「誰に向けての感謝か」で自然に使い分けるのが大切です。
この記事では、自治会や地域行事でよく登場する3つの言葉を整理し、
使い分け・場面別の判断・封筒マナー・金額の考え方までわかりやすくまとめます。
「御花」「寸志」「謝礼」はどう違う?
まずはそれぞれの言葉が、どんな場面で使われるのかを整理しておきましょう。
| 用語 | 主な場面 | 相手 | 表書き例 | 意味合い |
|---|---|---|---|---|
| 御花 | 神事・祭礼 | 神社・祭礼側 | 御花/お花代 | 神様へのお供え。人へのお礼ではない |
| 寸志 | 地域行事 | 協力者・役員 | 寸志 | 「わずかですが」の謙譲表現。感謝のしるし |
| 謝礼 | 講習会・式典 | 講師・来賓 | 謝礼/御礼 | 依頼に対する正式なお礼(対価的な意味合い) |
どれも「感謝を伝えるお金」ですが、誰に渡すかによって使う言葉が変わります。
つまり、
- 神様へ → 御花
- 仲間へ → 寸志
- 依頼相手へ → 謝礼
参考3つの言葉の違いをさらに詳しく整理した記事はこちら。
シーン別で見る使い分け方
地域行事では、形式よりも「自然で伝わること」が大切です。
ここでは、代表的な場面ごとの使い分けを紹介します。
秋祭り・神事の場合 → 「御花」
秋祭りや荒神祭など、神社や祭礼に包むお金は「御花(おはな)」です。
お供えの意味を持つため、人へのお礼とは区別します。
多くの地域では「御花代」と書くのが一般的です。
参考御花の金額や封筒選びは以下の記事で紹介しています。
清掃・地域行事の場合 → 「寸志」
清掃や餅つき、防災訓練などで協力してくれた人へのお礼は「寸志」が自然です。
「わずかですが」という控えめな表現で、金額よりも気持ちを重視します。
参考封筒の選び方や書き方をまとめた記事はこちら。
講習会・来賓対応など → 「謝礼」
講師を招いたり、来賓に挨拶をお願いした場合は「謝礼」または「御礼」を使います。
依頼に対する正式なお礼という意味合いがあり、寸志よりもフォーマルです。
参考講師や出演者への謝礼金額の目安はこちら。
封筒と表書きの基本マナー
言葉を正しく使えても、封筒で迷う人は多いものです。
自治会では「清潔で丁寧に」が基本。派手さよりも見た目の整いが大切です。
封筒の種類と使い分け
| 封筒タイプ | 主な場面 | 備考 |
|---|---|---|
| 紅白蝶結び | 清掃・協力など何度もある行事 | 繰り返しを祝う意味 |
| 紅白結び切り | 式典・講師謝礼など | 一度きりの正式なお礼 |
| 白封筒(のしなし) | 神事・御花 | シンプルで控えめに |
参考のし袋・白封筒の使い分け早見表はこちら。
表書きと金額の書き方
封筒の上段に「御花」「寸志」「謝礼」など、下段に団体名または氏名を記入します。
中袋がある場合は金額を中に、ない場合は封筒の裏面左下に小さく記載しましょう。
参考中袋なし封筒での金額の書き方はこちら。
金額の目安と会計のポイント
金額に正解はありません。大切なのは「無理せず、気持ちよく渡せる範囲」です。
地域の慣習や昨年の記録を参考に、バランスをとりましょう。
| 種別 | 一般的な相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 御花 | 1,000〜5,000円 | 祭礼の規模によって差あり |
| 寸志 | 500〜2,000円 | 感謝の気持ちが伝われば十分 |
| 謝礼 | 3,000〜10,000円 | 講師・出演者など依頼内容により調整 |
参考金額を旧字体で書く場合の一覧はこちら。
会計・記録の工夫
「誰に・いくら・どの名目で渡したか」を記録しておくと、次年度がぐっと楽になります。
領収書テンプレートを使えば、書式を統一できて便利です。
参考会計報告や記録に使えるテンプレートはこちら。
まとめ
「御花」「寸志」「謝礼」は、すべて“感謝を伝えるための言葉”。
どれを使うかで迷ったときは、そのお金が誰に向けられているかを意識すれば自然に決まります。
形式や金額の大小よりも、相手への思いやりが何よりのマナー。
地域行事は、人と人とのつながりの上で成り立っています。だからこそ「丁寧に伝えること」こそが一番の礼儀です。
この記事で紹介した内容を、
テーマ別に詳しく解説したシリーズはこちら↓